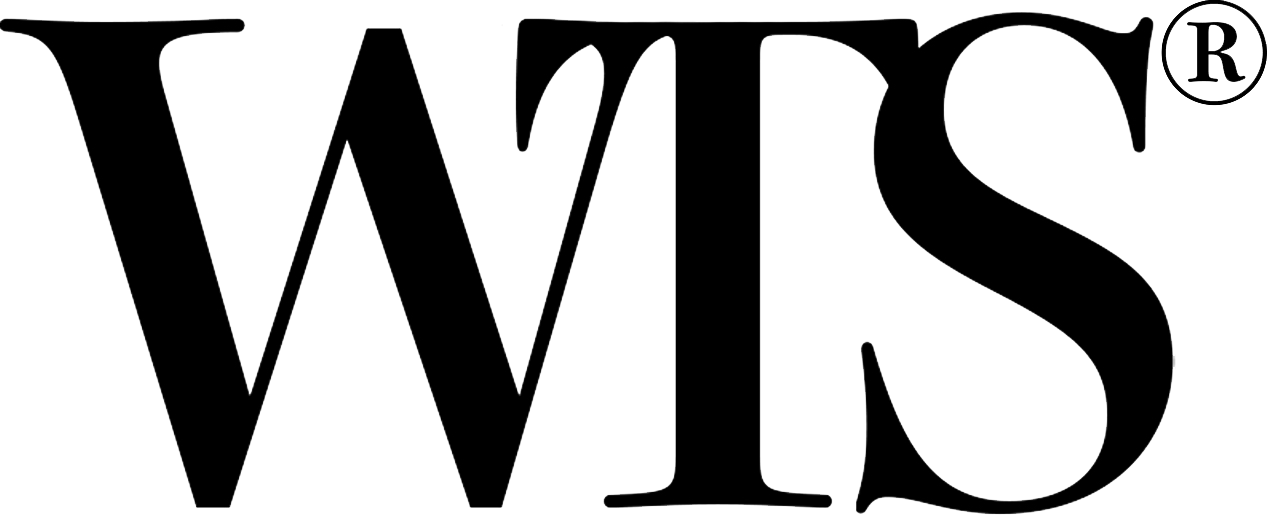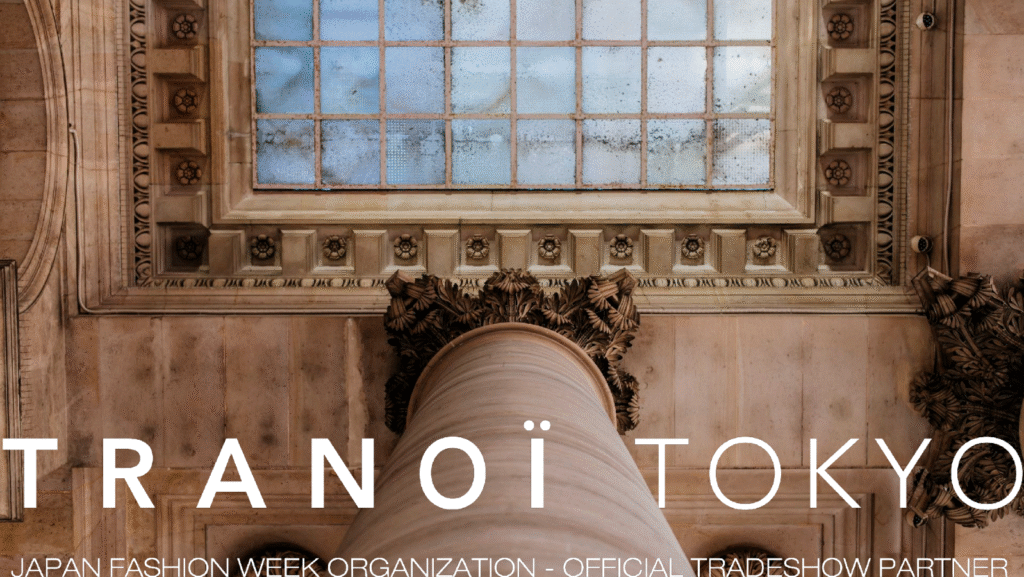
- Paris Fashion Weekが唯一認める合同展示会TRANOÏ。伝統と歴史を持つTRANOÏがなぜ新たな開催地を日本にされたのでしょうか?
TRANOÏ CEO Mr. Boris(以下B):日本は、TRANOÏにとって常に非常に重要なマーケットであり、来場者としても出展者としても大きな存在です。実際に、TRANOÏ Parisでは日本は来場者数で3位、出展ブランド数でも5位に入っています。
しかし、コロナ以降、日本からパリ・ファッションウィークへの来場者数が減ってしまい、それであれば私たちの方から日本へ出向こうと考えたのが、TRANOÏ TOKYOを立ち上げるきっかけでした。
開催地として東京を選んだ理由はいくつかあります。まず、東京はアジア全体のバイヤーにとってアクセスしやすいハブ都市であり、韓国、中国、台湾、シンガポール、ベトナムなど、さまざまな国から集まりやすいロケーションにあります。パリと比べても、移動のハードルが低いのは大きな利点です。
また、日本には現在、TRANOÏのように国際的なデザイナーを独自にキュレーションして紹介する展示会が存在していません。そのため、私たちの強みを活かしながら、ユニークなポジションを築くチャンスがあると感じました。
さらに、日本は国内の購買力が非常に高く、近年はインバウンド観光の効果も追い風となっています。日本ファッションウィークとの連携も視野に入れながら、東京の国際的なファッション都市としてのプレゼンスを高めていく。今がまさに、そのための戦略的なタイミングだと考えています。
- 2024年9月に記念すべき第一回を開催されましたが、実際に日本で開催されてどのような印象を受けましたか?
B:日本で初めて開催できたことは、本当にエキサイティングでした。
会場全体に強いエネルギーがあって、入り口に立った瞬間からその熱気を感じることができました。
来場者数も非常に多く、会場は終始人で賑わっていて、すごく活気がありました。
言語の壁については少し心配していたのですが、思った以上に自然にコミュニケーションが取れていました。
来場者の方々は、どのブランドのコレクションにも本当に興味を持って、じっくりと向き合ってくれていたのが印象的でした。
そして何より嬉しかったのは、ブランドと来場者の間にしっかりとしたつながりが生まれていたこと。
ビジネスの場というだけでなく、展示会の中で自然と“コミュニティ”のような雰囲気が育っていたのを感じました。
- 第二回を開催された際に第一回とどのような点を変えられたのでしょうか?
B:第2回目を終えて、前回と比べていくつか大きな改善ができたと思っています。
まず、TRANOÏ Parisの持つ国際的なネットワークやキュレーション力を活かして、よりグローバルなセレクションを強化しました。
その結果、前回よりも多くのインターナショナルブランドを招くことができて、全体の60%が海外ブランド、40%が日本のブランドになりました。
中でもフランスからは20ブランドが参加していて、ANDAM賞のファイナリストであるJEANNE FRIOTのような若手デザイナーから、LancasterやPRET POUR PARTIRのような歴史あるブランドまで、幅広い顔ぶれでした。
それから、会場の雰囲気づくりにも力を入れました。
ただ商談をする場ではなくて、もっとリラックスして、でも刺激があって、出展者と来場者が深く交流できるような空間を目指しました。
さらに、今回はアジア市場を意識したキュレーションも心がけました。
「TRANOÏ」と聞くと、どうしてもパリの展示会やその独特の雰囲気を思い浮かべる方が多いと思うんですが、TRANOÏ TOKYOはパリのコピーではなく、東京だからこそできるセレクションにしたかったんです。
ローカルの感性やニーズにしっかりと寄り添いながらも、グローバルに響くような展示会を目指しました。
- パリでのTRANOÏと東京での開催どのような点が異なると感じられましたか?
B:パリと東京、両方に共通しているのは、TRANOÏの根本にあるフィロソフィーやコンセプト。それはどちらでもしっかりと守られています。
その上で、東京で特に印象的だったのは、出展者のホスピタリティや温かさですね。
ただブースに立っているだけじゃなくて、すごく積極的に、しかもフレンドリーに来場者と関わってくれていたのがすごく印象に残っています。
あと、東京では出展者自身が「このイベントを一緒につくっている」という意識を自然と持ってくれている感じがありました。
自分たちのクライアントを積極的に招待したり、会場の空気づくりにもすごく貢献してくれていて、運営側との“共創”が本当に感じられました。
ファッションだけじゃなくて、カルチャーやライフスタイルの要素を組み込んでいるのも東京の特徴のひとつです。服だけを見せるのではなくて、もう少し広い文脈で魅せていくということを意識しています。
それから、東京のチームはパリに比べると規模は小さいんですが、その分、外部から本当に熱意を持ってTRANOÏを支えてくれるプロフェッショナルたちがたくさんいるんです。
そのおかげで、チーム全体に一体感があって、みんなが心からこのイベントを成功させたいと思ってくれている、そんな特別な空気が生まれていると思います。
- この9月は会場を代々木体育館に移し、規模を拡大して開催すると伺いました。第3回について教えて頂けますでしょうか?
B :はい、今年9月の第3回目は、TRANOÏ TOKYOの1周年という特別なタイミングでもあるので、ちょっとした節目のお祝いのような気持ちで準備しています。
今回は新しい会場として、代々木第一体育館に移ります。規模もかなり拡大していて、ウィメンズ・メンズ・ユニセックスのRTW、アクセサリー、ライフスタイルなど、約230ブランドをキュレーションしています。ブランドの出展国も30カ国以上に広がっていて、本当に“世界のクリエイティビティの祝祭”という感じになりそうです。
ファッションとカルチャーの融合というコンセプトも引き続き大切にしていて、今回はルーマニアのクリエイティブ集団「Future in Textiles Association」とのオープニングパーティーを予定しています。
来場者の面では、これまで通りVIPバイヤーを大切にしつつ、日本やアジア各国からインフルエンサーを招いて、SNSを通じた発信にも力を入れていく予定です。
それから、今回特に楽しみなのが、アフリカ、ルーマニア、トルコ、コロンビア、サウジアラビアなど、新興エリアからの12のコレクティブを招いていることです。過去最多のブランド応募があったことで、より選び抜いたクオリティの高いラインナップが実現できたと思います。
そして、TRANOÏ TOKYOはファッションだけじゃなく、カルチャーやライフスタイルも一緒に体験できるイベントを目指していて、今回もいろんな仕掛けを用意しています。
たとえば、パリ発のカルチャースポット「ofr.」とのコラボでカルチャー空間をつくったり、ユニバーサル ミュージックとの提携で音楽とファッションが融合したラウンジを展開したり、東京のレコードショップ「Adult Oriented Records」も参加してくれて、よりオルタナティブな文化の要素も取り入れています。
さらに、「武蔵國珈琲」や「Cocotte Cuisine」といったカフェコンテンツも加わって、会場全体の雰囲気をより豊かにしてくれると思います。
- アジアのハブになるような存在にしたいとのことですが、今後のTORANOIについて考えや構想を教えて頂けますでしょうか?
B:はい、TRANOÏ TOKYOをアジアのファッションシーンの中心的なハブにしていきたい、というのが私たちの大きな目標で、少しずつそのビジョンが形になってきていると感じています。
会場の規模が拡大することで、展示ブースだけにとどまらず、カルチャーイベントやブランドプレゼンテーション、キュレーションされた体験型のコンテンツなど、より多彩でダイナミックなプログラムを組めるようになってきました。
海外ブランドにとっては、TRANOÏ TOKYOは日本やアジア市場に本格的に入っていくための素晴らしいゲートウェイになりますし、実際に多くのブランドがここで新しいつながりを作っています。
一方で、日本のブランドにとっても、TRANOÏに選ばれるということ自体が「クオリティの証」になりつつあって、誇りを持って出展していただける場になってきたと感じています。
この高いクオリティは今後もキープしつつ、毎シーズン新しいアイディアや発見、フレッシュな空気を取り入れて、常に進化し続ける展示会でありたいと思っています。
もっと長期的な視点で言えば、私たちは従来の「展示会」という枠を超えて、ファッション業界そのものにもっと深く関わっていきたいと考えています。
バイヤーとのつながりはもちろん大事ですが、それだけでなく、スタイリストやフォトグラファー、インフルエンサー、カルチャー寄りのKOL(キーオピニオンリーダー)とも積極的につながっていきたいんです。
また、2つの展示会の合間の時期にも、何かしらイベントやコラボレーションを行うことで、年間を通じてTRANOÏの存在感を保ち、より多くのアジアのファッション関係者に関わってもらえるようにしていきたいと思っています。
最終的には、TRANOÏ TOKYOを単なる展示会ではなく、カルチャーとクリエイティブの交流のための“プラットフォーム”として育てていきたい。
そのために、リテーラーや様々な業界パートナー、クリエイターたちと一緒に、新しい形を作っていけたらと思っています。

Boris Provost
ボリス・プロヴォー
TRANOÏ CEO
パリのナイトライフやファッション業界でプレスオフィサーとして長年活躍した後、WSNの経営陣の一員として13年以上にわたり従事。2003年にWhoʼs Nextのマーケティング&コミュニケーションディレクターとしてWSNに入社し、その後、経営委員会メンバーとしてブランド戦略および国際展開ディレクターを務め、2016年まで同職を担当。
その後、ヨーロッパを代表する見本市主催企業Reed Exhibitions Franceに移り、3年間にわたりホスピタリティ&フード業界向けのB2BイベントEquip’Hotelの統括を担当。2019年初頭には、Reedのホスピタリティ&フード部門の責任者に就任。
2019年、ファッション業界に復帰し、TRANOÏのCEOに就任。2020年7月31日には、TRANOÏがGL eventsグループのファッション部門に統合され、Première Visionと並ぶ重要なポジションを占めることとなった。